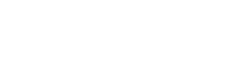コンピュータのメモリについて勉強したことまとめ!ROMとRAMについて
- 2019.01.03
- 未分類
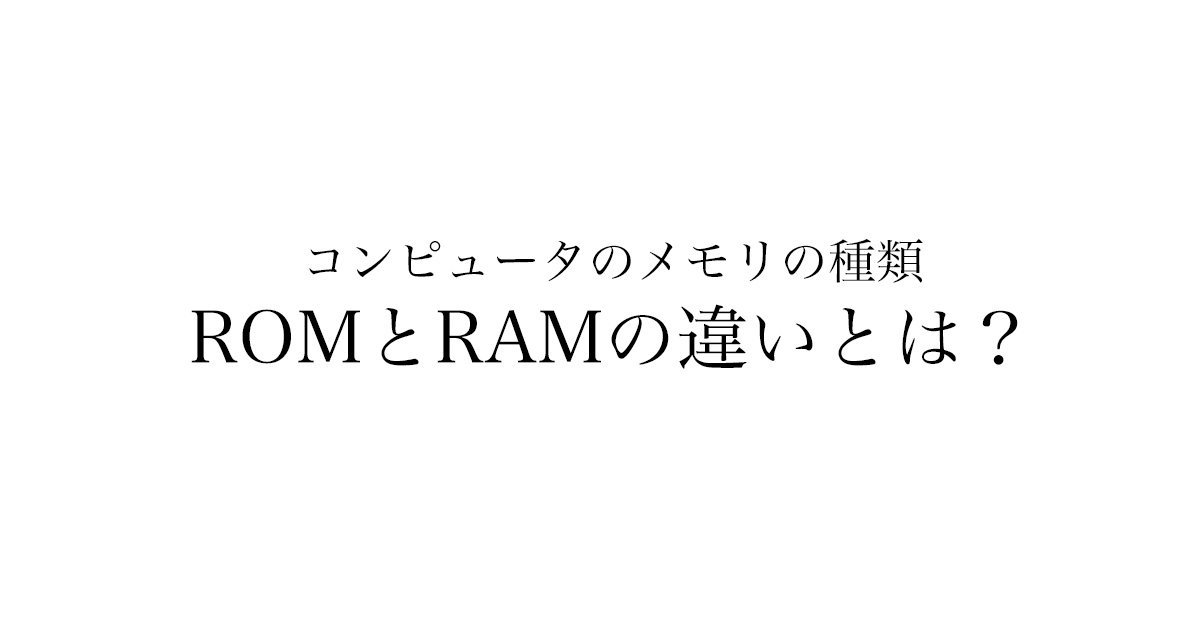
ご覧頂きありがとうございます!あまね(isaka122)です!
みなさんはスマホやパソコンに写真や文書などありとあらゆるデータを保存しますよね?
でも、なんでデータが保存できるのでしょうか?
それはコンピュータがメモリという記憶装置を持っているからなんです。
今日はそんなメモリについて調べてみたことをまとめます。
メモリとは
メモリとは、ディジタルデータを記憶する装置のことです。
読み出しと書き込みが行えます。
全体は8ビット=1バイトに区分され、それぞれのブロックはアドレスという番号によって区分されています。
プロセッサはこのアドレスを指定することでメモリにアクセスしているのです。
そして、メモリには大きく分けてROMとRAMがあります。
ROMとは
ROMとは、Read Only Memoryの略です。
工場で製造されたときに書き込まれたものがあとから変更できないメモリです。
一度書き込まれたものは消えることがないため、揮発性のメモリとも言われます。
さて、ROMには大きく2種類あります。
1つは、マスクROM。
本来の意味の、製造時に書き込まれたデータが絶対に書き換えることができないものです。
2つめは、PROM(Programmable ROM)です。
プログラミングできる、という名前の通りユーザーが書き換えることができます。
このPROMの種類として、
- 紫外線でデータを消して書き換えるEPROM(Erasable ROM)
- 電気的に削除して書き換えるEEPROM(Electrically EPROM)
- ブロック単位で消去可能なEEPROM(フラッシュメモリ)
に分類されます。
RAM
一方、RAMを見てみましょう。
RAMとは、Random Access Memoryで、ランダムにアクセスできるメモリのことです。
揮発性メモリとも言われます。
主記憶やキャッシュとして使われます。
こちらは大きく分けて、SRAMとDRAMに分けることができます。
SRAMとはフリップフロップ回路を用いて1ビットを記録するRAMです。
高速ですが、価格が高いというデメリットがあります。
DRAMとはコンデンサの電荷によって記憶します。
大容量、コストが安いというメリットがありますが、低速だったり、リフレッシュが必要だったりという欠点があります。
まとめ
以上、ここまでコンピュータで使われるメモリについてまとめてみました。
- 前の記事
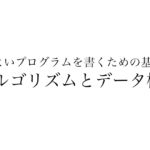
データ構造とアルゴリズムについて〜データ構造編〜 2018.12.28
- 次の記事
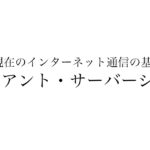
クライアント・サーバシステムとは? 2019.01.04